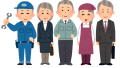日本の仏教における葬儀や法要で欠かせない儀式が焼香(しょうこう)だ。香を焚く行為は、仏様や故人の霊前に香りを供える供養の基本的な形であり、参列者の心身を清め、故人の冥福を祈る意味合いを持つ。
しかし、一見単純に見えるこの作法は、宗派によってその回数、作法、そして込められた教義的な意味が大きく異なる。
例えば、同じ「浄土」を説く宗派でも、焼香の回数には決定的な違いがある。
日本の主要な仏教宗派における焼香の作法を徹底的に比較解説し、それぞれの宗派がなぜその作法を採用しているのかを、教えの根幹から紐解いていく。
葬儀に参列する際に戸惑うことがないよう、宗派の正式なやり方と、一般参列者としての略式作法の両方を詳しく解説する。
1. 焼香の基本的な知識と意味
宗派ごとの違いを見る前に、焼香の基本的な形式と、その行為に込められた意味を理解しておく必要がある。
1-1. 焼香の三つの形式
焼香には、主に三つの形式がある。
葬儀の規模や場所によって使い分けられる。
- 立礼焼香(りつれいしょうこう):立ったままで行う形式で、椅子の並んだ葬儀会場や斎場などで最も多く用いられる。
- 座礼焼香(ざれいしょうこう):座布団などに座った状態で行う形式で、和室や寺院の本堂などで用いられる。
- 回し焼香(まわししょうこう):広い会場や自宅での葬儀などで、香炉を参列者に回して行う形式。香炉を隣の人に回し、自席で焼香を行う。
どの形式であっても、焼香の基本的な作法、すなわち「香をつまんで香炉にくべる」という行為自体は変わらない。
違いが出るのは、この「香をつまむ回数」と「押しいただく(おでこに掲げる)か否か」である。
1-2. 焼香が持つ二つの意味
仏教において、香を焚く行為は供養と浄化という二つの重要な意味を持つ。
- 供養: 香りの煙は仏様の食べ物(香食)と考えられ、故人の霊がその香りを食べて成仏できるように供えるという説がある。また、香りを供えること自体が仏様に対する敬意の表現である。
- 浄化(自浄): 仏前に進む前に、参列者自身の心身、特に嗅覚や口からの穢れを清めるという意味がある。焼香は、参列者が自らの心を清らかにして、仏様と向き合うための準備行為なのである。
2. 宗派別 焼香の作法と教義の背景
日本の主要な仏教宗派における焼香の作法と、その教義的な背景を比較する。
2-1. 真言宗・天台宗(密教系)
両宗派は、焼香の回数を3回とするのが正式な作法である。
- 回数: 3回(香を3回つまみ、3回とも香炉にくべる)
- 押しいただく: 押しいただく(おでこに掲げる)
- 教義的意味: 密教の教えである「三宝(仏・法・僧)」や、修行の三要素である「三密(身・口・意)」に供養するという意味合いが込められている。最初の1回は仏、2回目は法、3回目は僧というように、敬意を分ける意味合いもある。
2-2. 浄土宗
浄土宗は、回数に厳密な決まりを設けないという特徴がある。
- 回数: 1回または3回
- 正式な作法としては3回が基本だが、参列者が多い場合などは1回でも差し支えないとされる。
- 押しいただく: 押しいただく
- 教義的意味: 阿弥陀仏への信仰を重視し、念仏を唱えることが最も重要であると説く。焼香は、その念仏を唱える前の心身の浄化という位置づけが強いため、回数そのものにこだわる必要はないという考え方だ。心を込めて行うことが重視される。
2-3. 浄土真宗(本願寺派・大谷派)
浄土真宗は、他の宗派と比べて焼香の作法が最も特徴的で、回数も宗派内で分かれている。
本願寺派(お西)
回数:1回
押しいただかない
浄土真宗は阿弥陀仏の救いを信じ、浄土へ往生することは阿弥陀仏の力によって定まっている(他力本願)と考える。
そのため、焼香は供養や自力による成仏のためではなく、「ただ仏様にお参りさせていただく」という感謝の行為に過ぎず、回数や作法にこだわる必要がない。
大谷派(お東)
回数:2回
押しいただかない
大谷派も本願寺派と同様に他力本願を説くが、焼香は「仏に供える」という意味合いから2回行う。
1回目は「香」、2回目は「火」を表すとも言われるが、これも正式な教義ではない。回数に意味を込めず、形式として2回行うのが慣例だ。
両派とも、「押しいただかない」という点が共通している。
これは、焼香という行為が自力で悟りを開くための修行ではないため、押しいただくという自己の行為に意味を持たせないという他力本願の思想を反映している。
2-4. 曹洞宗・臨済宗(禅宗系)
禅宗も焼香の回数に特徴がある。
- 回数: 2回
- 1回目(主香): 仏様へ香を供える。これは必ず押しいただく。
- 2回目(従香): 火を消し、香を調整するためのもので、押しいただかない。
- 教義的意味: 禅宗は「坐禅」による自力での悟りを重んじる。焼香も修行の一環として捉えられ、香を供える行為を丁寧に区別する。最初の1回で敬意を示し、2回目でその状態を整えるという、「作法の実践」を重視する教えが反映されている。
2-5. 日蓮宗
日蓮宗も、真言宗などと同様に3回を基本とする。
- 回数: 3回
- 押しいただく: 押しいただく
- 教義的意味: 宗祖の日蓮聖人を尊び、お題目を唱えること(南無妙法蓮華経)が最も重要である。焼香の3回は、三宝(仏・法・僧)への供養や、三世(過去・現在・未来)の仏様に香を供えるという意味合いがある。
3. 一般参列者が知っておくべき作法の原則
宗派ごとの違いは上記のように多岐にわたるが、一般の参列者が完璧に作法をこなす必要はない。
以下の原則を押さえておけば、失礼にあたることはない。
3-1. 自分の宗派か、会場の宗派か
葬儀に参列する際、焼香の作法は「会場(喪家)の宗派」に従うのが原則だ。
自分の宗派と異なる場合は、会場の作法に合わせるべきである。
しかし、自分の宗派の作法に慣れている場合や、宗派が不明な場合は、無理に回数を合わせる必要はない。
最も無難な作法は「1回」であり、心を込めて行うことが重要だと考えられる。
3-2. 焼香の回数に迷った場合の「無難な作法」
宗派が分からない、または作法に迷った場合は、以下の「略式作法」で行うのが最も無難である。
- 回数: 1回(または2回)
- 押しいただく: 押しいただいても、いただかなくても良い
- 補足: 仏教の葬儀は故人の冥福を祈る場であり、作法の回数そのもので供養の心が決まるわけではない。一礼し、静かに1回焼香を行い、心を込めて合掌することが、最も大切な作法である。
3-3. 焼香の実際の手順(立礼焼香の場合)
- 遺族と導師への一礼: 焼香台に進む前に、遺族と僧侶に向かって軽く一礼する。
- 霊前への一礼: 焼香台の前で立ち止まり、遺影に向かって一礼する。
- 焼香: 香を指で少量つまみ、目の高さまで押しいただく(宗派による)。その後、香炉の炭の上にくべる。これを宗派の定める回数繰り返す。
- 合掌: 焼香を終えたら、遺影に向かって合掌し、深く一礼する。
- 遺族と導師へ一礼: 焼香台を離れ、再び遺族と僧侶に向かって一礼し、席に戻る。
4. まとめ:宗派の教えから学ぶ焼香の本質
焼香の作法は宗派によって多様だが、その回数や押しいただくか否かは、それぞれの宗派が故人の救済や悟りについてどのように考えているか、という教義の核心が反映された結果である。
- 自力救済(禅宗など): 焼香を修行の一環と考え、作法を丁寧に行う(回数に意味を持たせる)。
- 他力救済(浄土真宗): 焼香は仏の力に感謝する儀礼であり、作法に意味を持たせない(回数にこだわらない、押しいただかない)。
- 混合宗派(浄土宗など): 念仏が中心であるため、回数よりも心を重視する。
葬儀に参列する際は、自分の宗派の作法を優先しつつも、会場の作法に合わせて回数を調整したり、迷った場合は「1回、合掌」の略式で済ませるのが最も賢明である。
何よりも、故人の安らかな旅立ちを願い、心を込めて手を合わせるという焼香の本質的な意味を忘れないことが重要だ。