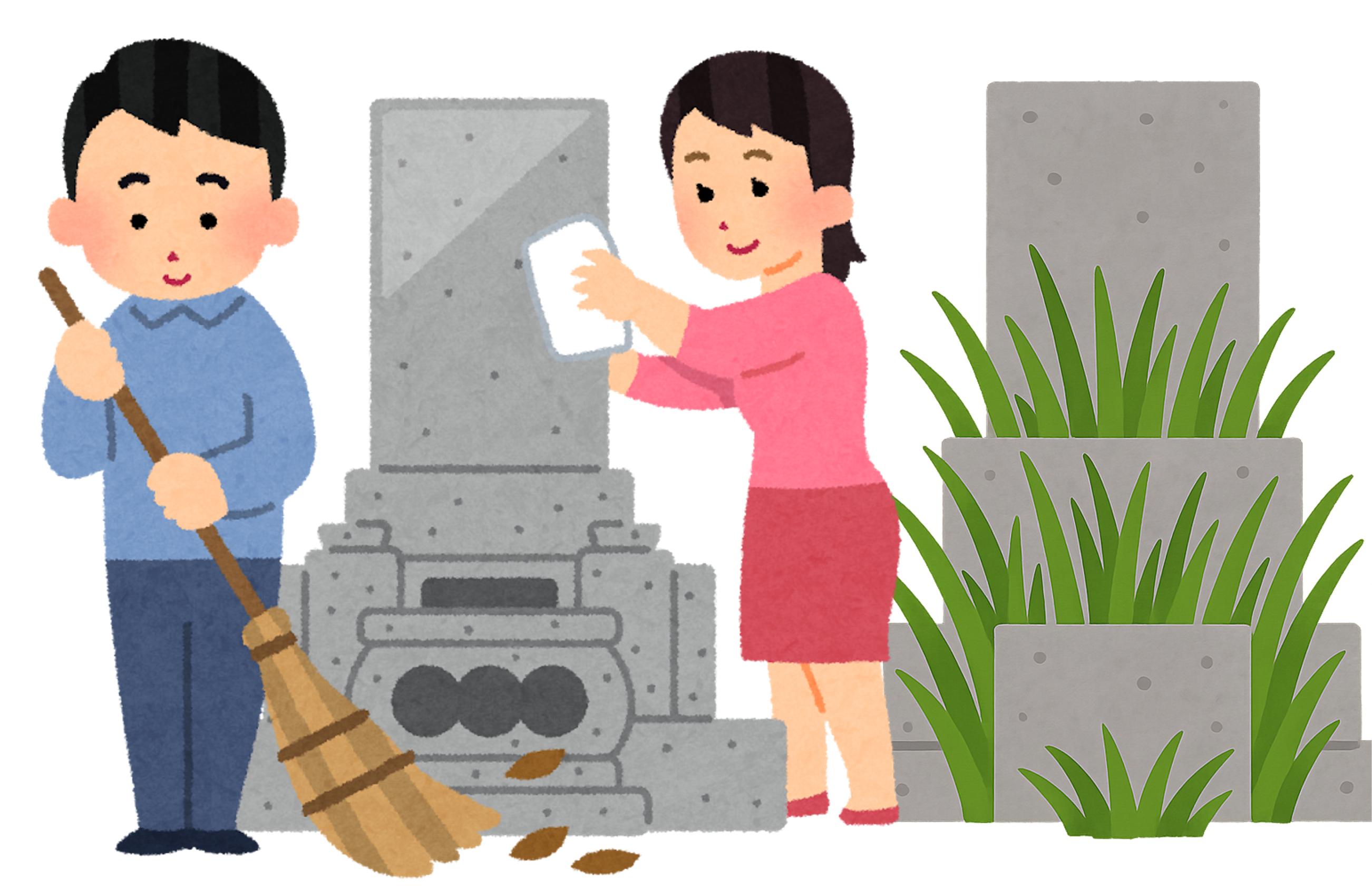はじめに
人は死を迎え、多くの場合は火葬という形で最期の別れを告げる。
葬儀という儀式の中で、故人との最後の時間を過ごす際、多くの人が「あの人が好きだったものを棺に入れてあげたい」と考えるであろう。
愛用した品々、想い出の詰まった贈り物、手紙や写真など、故人への尽きぬ思いを形として捧げたいという心情は、何物にも代えがたい尊いものである。
しかし、その善意が故人の旅立ちを妨げ、遺骨を傷つける可能性があることを知る者は少ない。
火葬の際、棺桶に入れてはいけないものという明確なルールが存在するのだ。
これは火葬場の都合や、単なる形式的な決まりではない。
故人を清らかな姿で送るため、そして環境への配慮から生まれた、大切なマナーなのである。
なぜ入れてはいけないのかという理由を掘り下げ、具体的な品目とその影響について解説する。
火葬の仕組みと、入れてはいけないものの原則
火葬は、棺を火葬炉に入れ、およそ800℃から1200℃という超高温で遺体を焼くことで、遺骨のみを残す工程である。
この火葬のプロセスを理解することで、なぜ入れてはいけないものがあるのかが明確になる。
入れてはいけないものの原則は、主に以下の五つに分類される。
* 爆発の危険があるもの:火葬炉内で急激な圧力変化を起こし、炉の破損や作業員の負傷を引き起こす。
* 燃えにくい、あるいは燃え残るもの:高温でも燃焼せず、遺骨と共に残ってしまう。
* 有害物質を発生させるもの:燃焼時にダイオキシンなどの有害ガスを放出し、環境汚染を引き起こす。
* 遺骨を汚したり、変色させたりするもの:高温の熱で溶けたり、煤を発生させたりして、遺骨の美しさを損なう。
* 不完全燃焼の原因となるもの:水分を多く含んだり、密度が高いものは、火葬の進行を妨げる。
これらの原則に沿って、具体的な品目を見ていこう。
現代社会の落とし穴:爆発の危険があるもの
故人が生前愛用していた品々の中には、現代社会ならではの危険物が潜んでいる。
その最たるものが、リチウムイオン電池を内蔵した電子機器だ。
スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリー、電動歯ブラシ、電気シェーバー、補聴器、電子たばこ…
これらは日常に欠かせないものとなり、故人も最期まで手放さなかったかもしれない。
しかし、これらの内部に搭載されたリチウムイオン電池は、高温になると内部でガスが発生し、膨張して爆発する危険性がある。
火葬炉は密閉された高温の空間であり、その中で爆発が起きれば、炉の壁や扉が破損し、火葬のやり直しを余儀なくされるだけでなく、火葬場の職員に致命的な怪我を負わせる可能性も否定できない。
故人を思う気持ちが、他者の安全を脅かすことになってはならないのだ。
また、意外な盲点として、スプレー缶やライターも同様に爆発の危険物である。
故人が愛用していたヘアスプレー、殺虫剤、カセットボンベなどは、絶対に入れてはならない。
これらの危険物は、火葬場への持ち込みそのものが禁じられている場合がほとんどである。
故人の愛用品をどうしても入れたい場合は、中身を抜き、火葬場の許可を得た上で、空の容器だけを入れるという方法もあるが、基本的には避けるべきである。
遺骨を傷つけ、変形させるもの:ガラスと金属
故人の眼鏡や指輪、腕時計を棺に入れたいと考える遺族は多い。
しかし、これらも火葬には適さない品々である。
ガラス製品
眼鏡のレンズ、香水瓶、ガラス製のコップなどは、高温の火葬炉に入れると溶けて液体となる。
そして、溶けたガラスは遺骨に付着し、冷えると遺骨を覆うように固着してしまう。
このガラスを取り除くことは非常に困難であり、故人の清らかな遺骨に傷をつけることとなる。
また、ガラスが不均一に溶けることで、火葬が不完全になる原因にもなりうる。
金属製品
指輪、腕時計、入れ歯、眼鏡のフレーム、金属製の装飾品など、故人が身につけていた金属製品も同様に火葬には向かない。
特に、ステンレスやプラチナ、金などの高融点金属は、火葬炉の温度でも完全に燃え尽きることがなく、遺骨と一緒に残ってしまう。
遺族がこれらを形見として残したいと考える場合もあるが、火葬の過程で熱によって変形したり、遺骨に付着したりするため、元の美しい形で残すことは難しい。
また、ペースメーカーのような医療機器は、電池が内蔵されているため、爆発の危険性もある。
故人の体に埋め込まれたものは、事前に申告することが義務付けられている。
環境汚染を引き起こすもの:プラスチックと化学繊維
故人への最後の贈り物として、お気に入りの洋服やバッグ、CDなどを棺に入れたいと考える人も多い。
しかし、これらの素材も環境への影響から、火葬には適さない。
プラスチック製品
ビニール製のバッグ、おもちゃ、ペットボトル、CD、DVDなどは、プラスチックを主成分としている。
これらは燃焼時にダイオキシンや塩化水素といった有害ガスを発生させる。
現代の火葬炉は排ガス処理装置を備えているが、それでも有害物質の排出をゼロにすることはできない。
故人を送る行為が、地球環境を汚染することにつながってはならないという配慮が必要だ。
化学繊維の衣類
故人が好きだったポリエステルの服やナイロンのストッキングなども、燃焼時に有毒ガスを発生させたり、高温で溶けて遺骨にまとわりついたりする可能性がある。
故人に着せる死装束や棺に入れる副葬品は、綿や麻、絹といった自然素材で作られたものが推奨される。
不完全燃焼と、遺骨の美しさを損なうもの
棺に入れるものの中には、火葬の進行を妨げ、遺骨を汚す原因となるものもある。
水分を多く含むもの
故人が好きだったスイカやメロン、ペットボトルのお茶などを入れることはできない。
これらの水分は火葬炉の温度を下げ、燃焼を妨げる。
また、不完全燃焼により大量の煤が発生し、遺骨に付着して黒く汚してしまう。
特に、大量の生花や、水分を含んだ分厚い本なども同様の理由で避けるべきである。
生花は、火葬場の規定に従い、少量であれば許可される場合がある。
分厚い書籍や布団
故人が大切にしていた愛読書や、愛着のある布団などを棺に入れることは、不完全燃焼の原因となる。
これらは密度が高く、火葬炉の火が回りきらずに燃え残る可能性がある。分厚い本は、数枚のページだけをちぎって入れるなど、量を調整する必要がある。
遺族の想いと、故人を偲ぶ代替案
故人が大切にしていた品を棺に入れることができないのは、遺族にとって非常につらいことである。しかし、このルールは決して故人への思いを否定するものではない。
むしろ、故人の旅立ちを最も美しい形で実現するための、大切な配慮なのだ。
愛用していた品々を棺に入れられない場合、その想いはどうすればよいのか。
代替案を考える
* 写真として残す: 故人の愛用品を身につけている写真や、品物そのものの写真を撮り、棺に入れてもらう。
写真であれば燃焼に影響はなく、故人の生きた証を共に送ることができる。
* 形見として大切にする: 故人が大切にしていた品は、棺に入れるのではなく、遺族が形見として引き継ぎ、大切に使い続けることが最高の供養となる場合もある。
* 故人のそばに置く: 葬儀会場では、棺のそばに故人の愛用品を飾るスペースが設けられていることもある。
故人のそばに一時的に置くことで、別れの気持ちを伝えることができる。
いずれの場合も、大切なのは「故人を思う心」を形にすることであり、物理的な「モノ」ではない。故人は、遺族のその気持ちを感じて安らかに旅立つであろう。
故人への最後の贈り物は、清らかなる旅立ち
火葬の際に棺桶に入れてはいけないものには、明確な理由がある。
それは、故人の遺骨を美しく残すため、火葬場の安全を守るため、そして環境を汚染しないためだ。
これらのルールは、故人を心から尊重し、清らかなる姿で送るための、愛ある配慮に他ならない。
故人への最後の贈り物は、形あるモノではない。
故人を思い、その旅立ちを心から願い、静かに見送るその気持ちこそが、何よりも尊い贈り物なのである。
故人が安らかに、そして清らかな姿で旅立てるよう、副葬品のルールを正しく理解し、最期の別れを慈しみをもって迎えることが、遺族にできる最高の供養であろう。