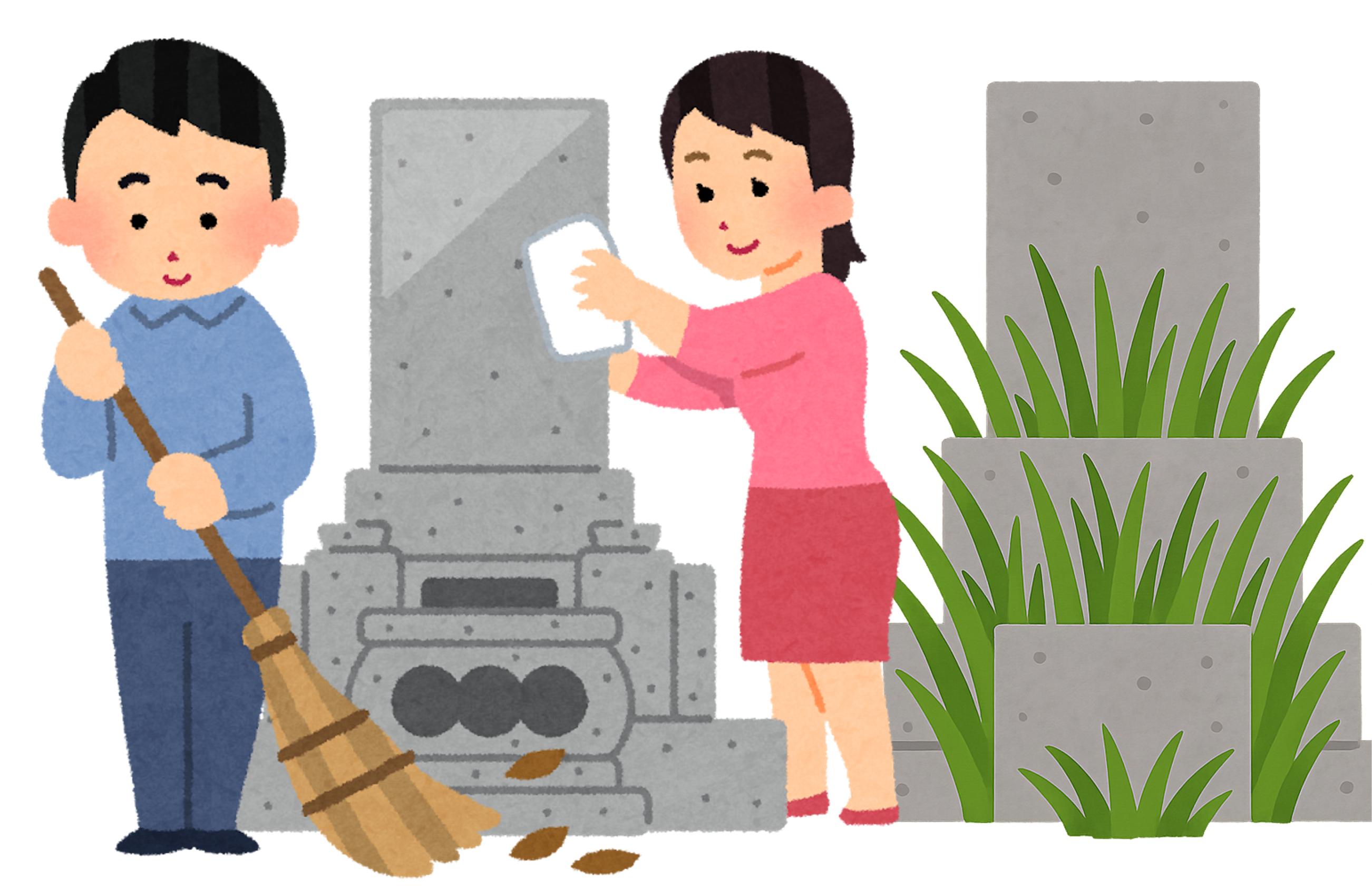火葬を終えた後に行われる「お骨上げ(拾骨)」は、葬送儀礼の中でも特に印象的な場面である。
遺族が竹製の長い箸を使って遺骨を拾い、骨壺へ納める光景は、多くの人が一度は目にしたことがあるだろう。
しかし「なぜ箸を使うのか」「どの骨を拾うのか」といった意味や作法について、正確に知る人は少ない。
本稿では、その起源や象徴性、宗派や地域による違いまでを整理しながら、お骨上げの意義を改めて考えてみたい。
遺骨を拾う流れと喉仏の意味
火葬が終わると、炉から取り出された遺骨は灰と分けられ、係員が台に並べてくれる。
すべてを遺族が拾い上げるわけではなく、最初に喪主や近親者が主要な骨を拾い、残りは火葬場の職員が骨壺へ収めるのが一般的だ。
時間短縮や安全面への配慮であり、形式を欠くものではない。
お骨上げの中でも特に重んじられるのが「喉仏」である。
実際には頸椎の一部だが、形が仏が合掌する姿に似ているとされ、最も神聖な部位と考えられてきた。
この骨を拾うのは喪主の役割とされることが多く、葬儀の中でも特別に象徴的な瞬間となる。
火葬場によっては喉仏や大腿骨をあらかじめ分け、部位を説明してから拾骨を始める場合もある。
箸を使う理由〜実用と象徴
お骨上げに箸が使われる理由は二つある。
第一に実用面で、骨を直接手で触れるのは衛生的でなく、また骨は高温で焼かれて脆くなっているため、道具で扱う必要がある。
竹製の長い箸は軽く、先端が平らで骨を欠けさせにくいため最適とされてきた。
第二に象徴面だ。箸(はし)と橋(はし)をかけ、「この世からあの世へ渡す橋」としての意味が込められている。
仏教で説かれる三途の川を、故人が迷わず渡れるように祈る心がそこに重ねられている。
単なる道具ではなく、故人の旅立ちを支える象徴的な媒介なのだ。
箸渡しの儀礼
お骨上げでは二人一組で骨を挟み、箸から箸へと手渡す「箸渡し」が行われることがある。
これは故人を家族で支え合いながら送り出す共同作業であり、「縁を結び直す」あるいは「最後の別れを告げる」という意味を持つ。
日常生活で箸から箸へ食べ物を渡すのを忌み嫌うのは、この儀礼を連想させるからだ。
つまり葬儀では正しい所作であり、日常では避ける作法という関係にある。
ただし、地域によっては一人が骨を拾い受け皿に置き、次の人が壺へ納める方法を取る場合もあり、どちらが誤りというものではない。
お骨上げの順序と作法
拾骨には大きく三つの要点がある。
第一に「誰が拾うか」。最初の一骨は喪主が拾い、その後近親者が続く。
高齢者や体調の悪い人は無理に行わず、拝礼だけでも差し支えない。
第二に「どの順序で納めるか」。多くの地域で足から頭へと下から上へ納めていく。
壺の中で逆さまにならないよう配慮する意味があるが、地域によって異なるため当日の指示に従うのが確実である。
第三に「すべてを拾う必要はない」という点だ。
遺族は主要な骨を中心に拾い、残りは職員が丁寧に納めて整える。
これは省略ではなく、安全と尊厳を守るための合理的な分担である。
箸の材質と形
拾骨用の箸は竹製が多い。竹は清浄の象徴であり、空洞を持つ姿は「魂がまっすぐ浄土へ昇る」ことを意味するとされる。
先端が鋭くないのは骨を傷つけないためであり、食事用の箸との違いを示す役割もある。
地域によっては金属製のトングを使う場合もあり、必ずしも一律ではない。
歴史的背景
お骨上げの起源は仏教にさかのぼる。釈迦の遺骨を弟子たちが分け合って供養した故事が日本に伝わり、平安時代には貴族の間で儀式化した。
江戸時代になると庶民にも広がり、今日まで受け継がれている。死者を敬い、家族が最後に直接手をかける儀礼として定着したのだ。
宗派や地域による違い
実務上は火葬場の方式に左右されるが、宗派によって意味づけに違いがある。
たとえば浄土真宗では、阿弥陀如来の他力によって救われるという教えから「遺族が骨を拾って導く」という発想を強調しない傾向がある。
ただし実際の火葬場では一般的なお骨上げが行われるため、宗派によって極端に異なるというよりも「所作の解釈」が違うと理解するとよい。
また、関東と関西では骨壺の大きさや収め方に違いがある。
関東では全骨を納める大きな壺を用いるのに対し、関西では主要骨を中心に納める傾向がある。文化や土地事情の違いが反映されている例といえる。
注意すべき点
お骨上げにはいくつかの注意点がある。
まず、食事用の箸は使わない。生者の日常と死者の儀礼を混同しないためである。
また、地域によっては箸渡しを「縁起が悪い」とする慣習もあり、その場合は受け皿を介して納める形が採られる。いずれにしても当日の係員や僧侶の指示に従うのがもっとも大切である。
服装や心構えも重要だ。
指輪やブレスレットは外し、動きやすい喪服で臨む。
子どもが参加する際は保護者が補助し、無理に行わせない。火葬場内での撮影は基本的に控え、静粛を守るのが望ましい。
まとめ
お骨上げは、遺族が故人に手を添える最後の儀礼である。
そこには実用的な意味だけでなく、三途の川を渡す「橋渡し」の象徴性や、家族の絆を再確認する精神的な意義が込められている。
箸は単なる道具ではなく、現世と彼岸をつなぐ象徴であり、感謝と別れを託すための媒介だ。
形式に囚われる必要はなく、最も大切なのは静かに手を合わせ、故人の旅立ちを見守る心である。
お骨上げの作法を理解することは、残された者が安心して別れを受け止め、人生の区切りを整えるための大切な準備でもあるのだ。